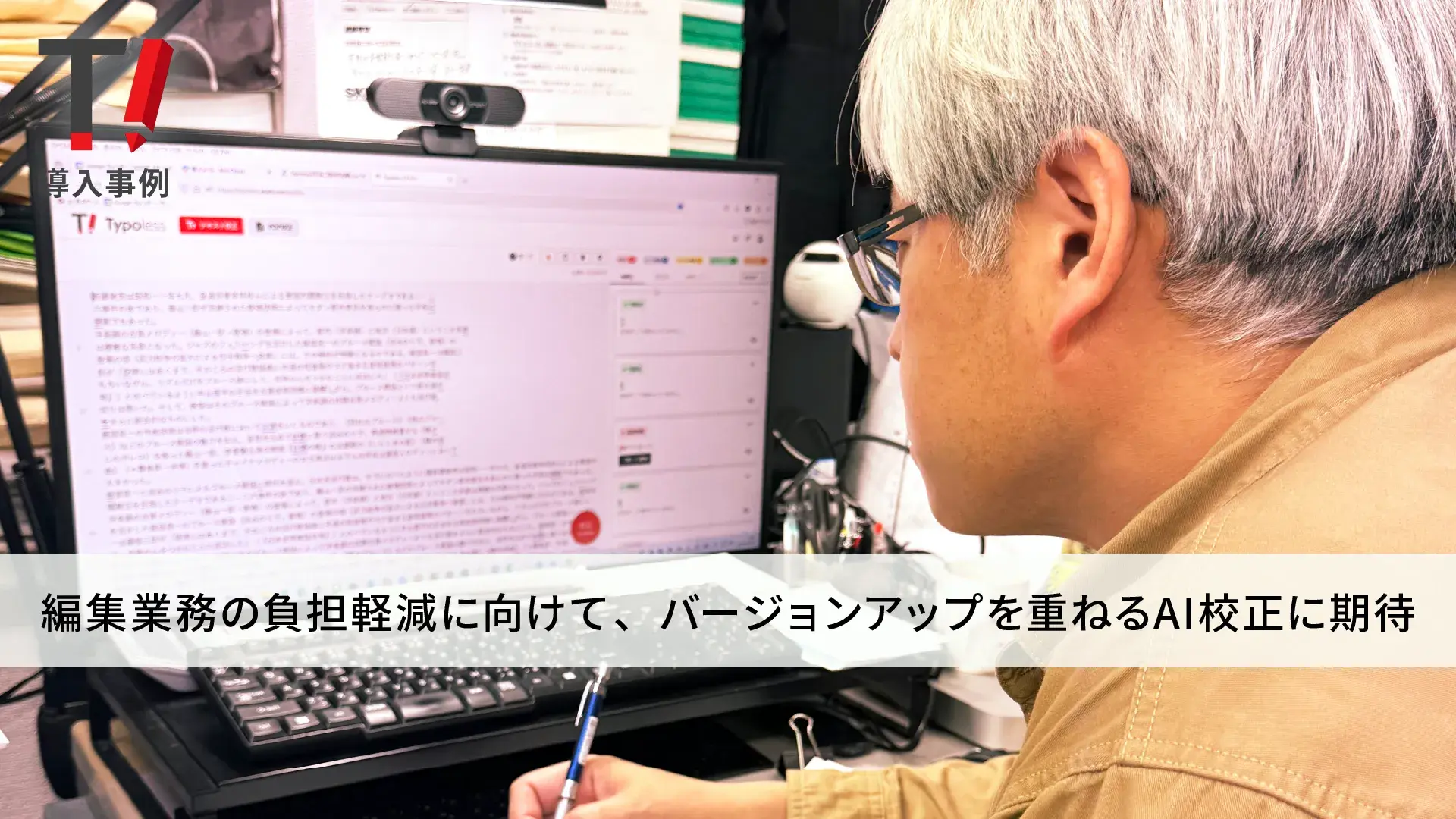Typoless 導入事例 | 業種:メディア
ダ・ヴィンチWeb編集部 様(株式会社KADOKAWA 様)
書き手とメディアへの信頼を守り、文章の質も向上

- 校正依頼のコミュニケーション工程を減らし、一瞬で修正箇所を指摘
- 人間が見落としがちなミスをAIが検出、読みやすさもサポート
- 文章の書き手もメディアも、文章のクオリティー向上が信頼に直結
書籍やコミックに関する情報を、紙やデジタルの垣根を越えて提供している人気サイト「ダ・ヴィンチWeb」。人気タレントや作者のインタビュー、書籍のレビューや連載マンガなどを毎日発信しており、月刊誌の『ダ・ヴィンチ』と同様に媒体として独自の地位を築いている。リテラシーの高いサイト訪問者に対して、正確な日本語を届けることは、コンテンツの信頼性を担保するうえで重要となる。月に千数百本の記事を配信するサイトの運営に、文章校正AI「Typoless」がどのような役割を果たしているのか、金沢俊吾編集長に聞いた。
滞在時間の長い、しっかりと読んでもらえるメディア
――「ダ・ヴィンチWeb」に掲載されている文章の内容を教えてください。
金沢俊吾編集長(以下「金沢」) 本のレビューやインタビュー、マンガの連載や試し読みなどを中心に、本を紹介するメディアというのが基本。タレントさんのエッセーやウェブオリジナルの記事も、広く捉えると読み物だという考え方です。家の中で楽しめるアニメやエンタメも広く扱っていていますが、しっかりとした読み物を求めるユーザーに楽しんでいただけるものを作っているサイトだと思います。
――雑誌の『ダ・ヴィンチ』とコンテンツは異なるのでしょうか?
金沢 雑誌の記事を一部転載しているものもあります。ただ、編集部は基本的に別組織で、ほとんどがオリジナルのコンテンツです。
――メディアとしての特性は何でしょうか?
金沢 2千字ぐらいの記事が多く、1記事あたりの滞在時間が非常に長いんです。平均しても1、2分で、インタビューだと4分ほど。何かを紹介するにしても、その分野が得意で思い入れも深いライターが、丁寧に長めの文章を書いています。そこに編集もしっかりと入って、時間をかけて作っているからこそ、最後までちゃんと読んでもらえるようになったという気がしています。

人間の校正にはない「Typoless」のスピード感と気軽さ
――貴社で「Typoless」を使うようになったきっかけは?
金沢 上司からその存在を聞かされたのは、私が2023年10月に編集長に就任してしばらく経ってから。編集部で採用するかを決める前に、個人で使ってみることになりました。私自身もライターとして取材や執筆を行うので、使い勝手を見てみようと。当然ながら、トライアルを経て契約をお断りする可能性もありました。
――数カ月後には正式に「ダ・ヴィンチWeb」「ウォーカープラス」「毎日が発見ネット」の3つのメディアの編集部で採用いただきました。金沢さんが「Typoless」を校正業務で使えそうだと思ったポイントは何ですか?
金沢 最終的には、人間とAIとの差になってくると思います。人間が校正した場合のミスは、完全になくすことはできません。その人が悪いのではなく、ヒューマンエラーは絶対に起こるので。もう一つは、人間に発注するためのコミュニケーションのひと手間がいらないこと。今までメールでお願いする際に「お世話になっております」と打ち始めた頃には、もう既にTypoless の校正が終わっていて。その結果をすぐに見られるスピード感と気軽さはありがたいですね。
見落としがちな脱字も指摘し、記事のクオリティーが向上

――「Typoless」導入前は、どのような校正の体制でしたか?
金沢 人間による校正は、2名いる外部の校正者に都度発注する仕組みでした。人間ならではの良さと課題があって、良い面は、彼らは文章を見るプロなので、専門用語や固有名詞などの校正も任せられるところ。記事全体のクオリティーに対してアドバイスいただけることで、若手編集者も助けられています。課題は、個々の校正者でブレがあったり、コミュニケーションも含めて編集者との相性が問われたりすることです。
――現在は人の手による校正と「Typoless」を併用されているそうですが、どう使い分けていますか?
金沢 急いで掲載しないといけないニュースなどの記事は、最低限の時間で校正できる Typolessがとても有効です。一方でマンガの校正や、作品のキャラクター名の確認などは、人間に発注しています。編集部としては、どちらかの校正は必ずかけるという運用です。何度も修正が入った原稿などは、両方の校正をするケースもあります。
――具体的な導入効果を教えてください。
金沢 確実に言えるのは、校正を発注するコミュニケーションコストが減り、編集部員の時短になったことです。大きな誤植などはもともと少なかったのですが、導入以降は現在まで出ていないですね。校正をかけているかいないかは、メディアとしてのクオリティーに直結しますし、一つ一つの記事のクオリティーも上がっていると考えています。また、炎上には非常に気をつかっているので、「炎上リスクチェック」の機能も活用しています。
――校正で指摘される誤りは、どのようなものが多いですか?
金沢 一番よく見つかるのは「脱字」です。キーボードで文字を打つと、脱字はどうしても起きやすく、読み直しても気付かないものです。有名な話で、単語の最初と最後の文字が合っていれば、中間の文字がいくつか変わっていても文章が読めてしまうケースがありますよね。それと同じで、人間の脳内で文字を補完してしまうんです。そういう見落としがないのはAIの長所であるとも言えます。
「良文サポート」で文章の質もアップ
――ライターとしても「Typoless」を利用された実感は?
金沢 個人で校正ができるというのは大きいですね。ちょっとした誤字脱字が、やっぱり一番恥ずかしいですから。自分で原稿を書いている時は、極端な時には送る10分前にTypolessをかけて、誤字脱字だけを直して送るということもできます。
――2024年5月に「良文サポート」の機能も追加されました。
金沢 100文字より長い文章や、助詞の連続は確かによくあります。それを指摘してくれるのは素晴らしいと思いますね。一文が長すぎると、読んでいる方も頭がついていきにくいので。接続助詞の「~たり」は2回以上使わなければいけないという指摘も、つい忘れがちですね。

――プロの方々も意外に気付かないものなんですね。
金沢 どんなに素晴らしい原稿を書いても、単純な間違いが1個や2個あると、それだけで信用が低くなってしまうのは非常にもったいないと思います。ただ、そういうミスは編集者や校正者などの客観的な視点がなければ、気付きにくいものです。そこにAIが関わることで文章のクオリティーが上がり、書き手としての評価も上がるのであれば良い。こっそりTypolessを使ったことを自分の手柄にしちゃえばいいんですよ。
――文章に携わる人に「Typoless」はどんな存在になっていくでしょうか?
金沢 いろいろな人がSNSなどでテキストを発信しやすくなったからこそ、プロ以外でも良い文章を求められる機会が増えていると思います。 Typolessは、書き手自身も校正をかけられるようになったのが大きなアドバンテージ。我々のようなメディアはもちろん、企業の社長や広報担当者なども含めて、使っていない人は試してみてもいいのではないでしょうか。
(掲載内容は2024年6月取材当時のものです)
ダ・ヴィンチWeb
株式会社KADOKAWAが運営している「本のポータルサイト」。漫画や小説、実用書などあらゆるジャンルの本を紹介している。2010年に文芸雑誌『ダ・ヴィンチ』が電子書籍の情報を発信するサイトとしてスタートし、オリジナルのコンテンツの拡充を重ね、2022年には現在の名称に変更した。月に5~6千万PV。多くの連載エッセーやマンガが書籍化されている。
【URL】
https://ddnavi.com/